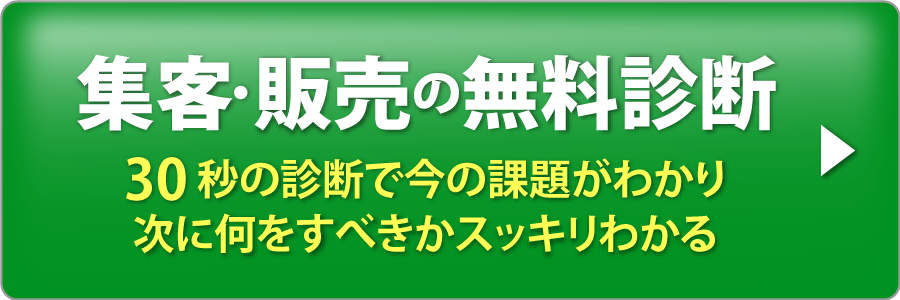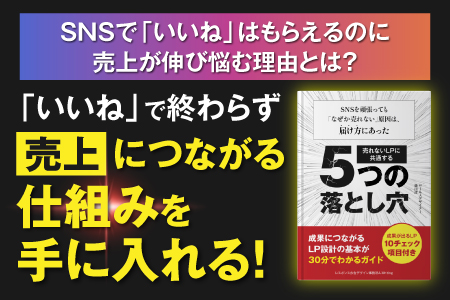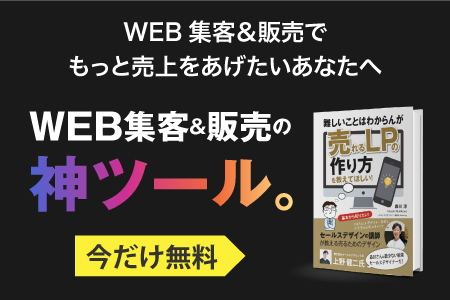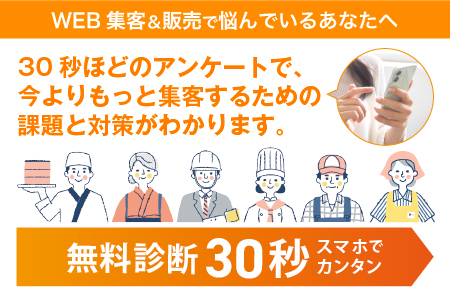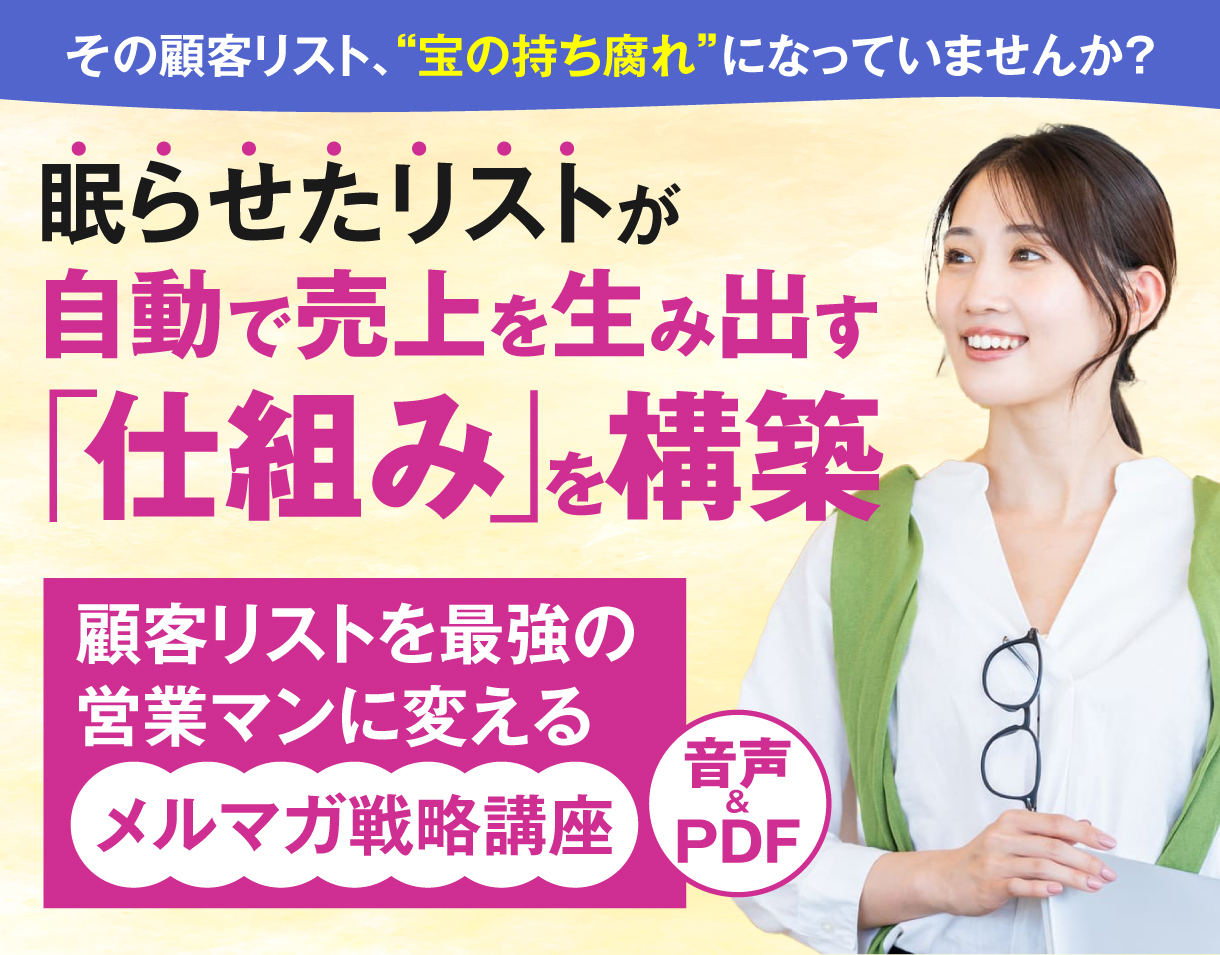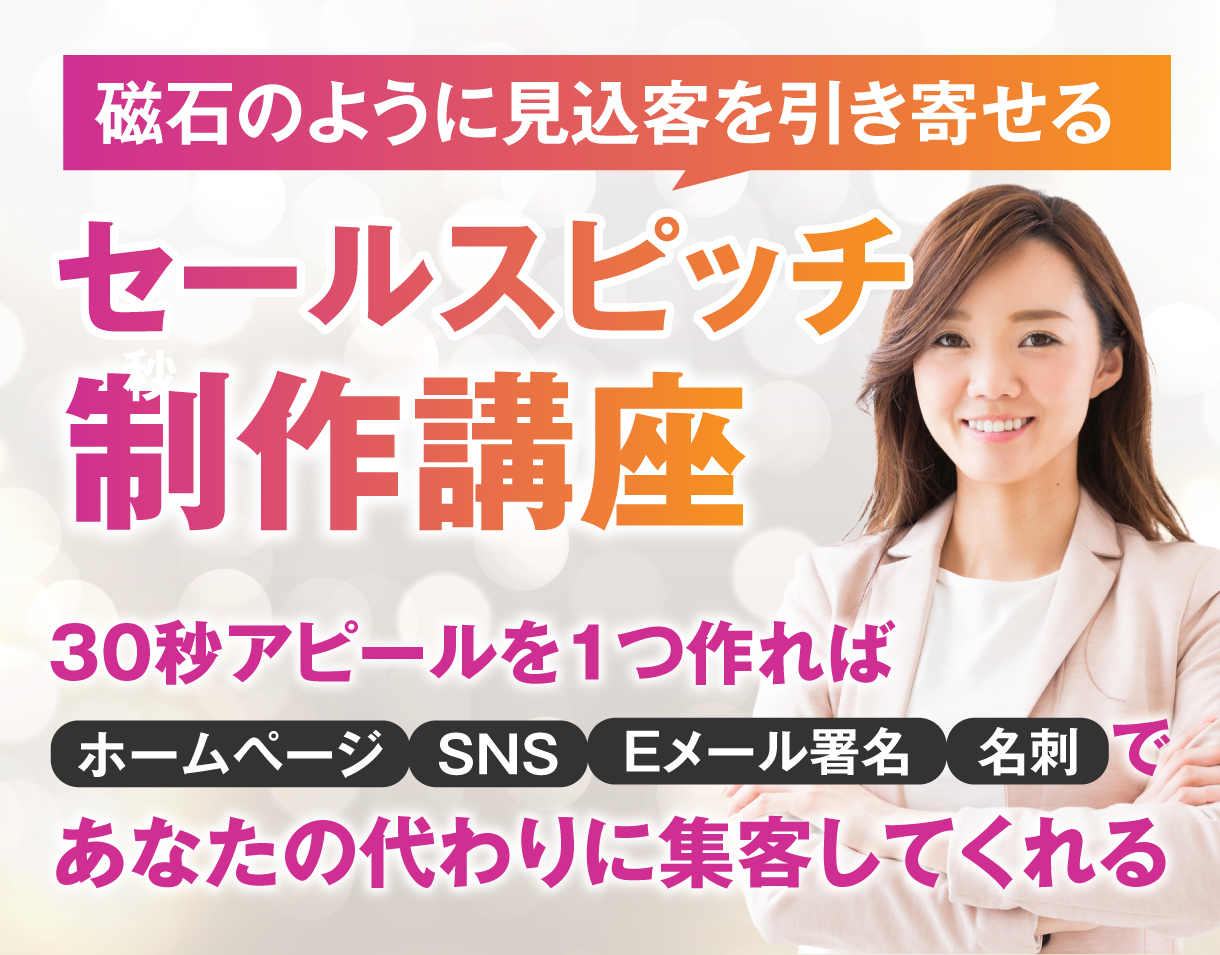大学教育にも採用
僕も最初は信じられませんでした。
きっとあなたも同じだと思います。
ですが、この方法を知って、1年に1冊も本を読まなかった僕でさえ毎日、気軽に本が読めるようになったのです。
なぜか?その最大の秘密は、日本の大学教育にも採用された『先行オーガナイザー』という速読法にありました。
テスト
まずはこのテストをしてみてください…
[テスト1]次の四文字を並び替えて、正しい言葉を作ってください。
- わりまひ
- あんえこ
- たくしつ
- どんすた
- こきひう
[テスト2]並び替えて『食べ物』の名前にしてください。
- おれつむ
- りきとや
- かおぴた
- あかげら
- てからす
さて、どっちの方が速く答えを出せたでしょうか?
きっとテスト②の方が、簡単だったのではないでしょうか?
実は、このテストにこそ、速読テクニックの1つが隠されています。
どういうことかと言うと、、、
速読テクニック「先行オーガナイザー」
きっとほとんどの人が②の方が簡単だったと思うのですが、、、
①と②では、何が違ったのでしょうか?
テスト①では、何の法則もない4文字が並んでいたのに対して、②では、「食べ物」と先にテーマが決まっていました。ここがポイントです。
つまり、人間の脳は、最初にある程度「枠組み」を作ってあげると、情報を素早く処理出来るようになるということです。
逆に言うと、情報の処理が遅い時は、この「枠組み」が頭に無いということです。(この枠組みのことを「先行オーガナイザー」と言います)
そしてこれは、読書でも同じことが言えます。
読書スピードが速い人は、あらかじめ本の内容の「枠組み」を作っています。
本で言うところの、章のタイトルや小見出しが「枠組み」に当たります。
一方で、読むスピードが遅い人は、見出しやタイトルを、本文と同じように読み流してしまいます。
これだと、脳の中に「枠組み」を作ることが出来ません。
本文を読みながら、「今何の話をしているのか?」と考えながら読んでいるので、当然、読むスピードが遅くなってしまいます。
見出しが出てきたら、一度立ち止まって、そこまでの流れを軽く振り返る習慣をつけましょう。
たったそれだけで、後に続く文章をサラッと流し読みしたとしても、しっかりと理解・記憶出来るようになるようです(^-^)
ぜひ試してみてください(^_^)/