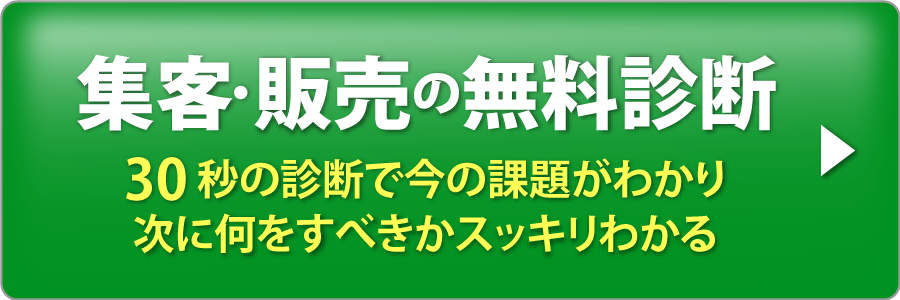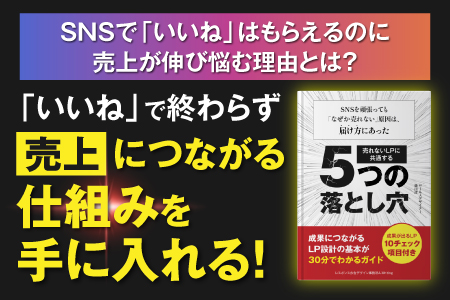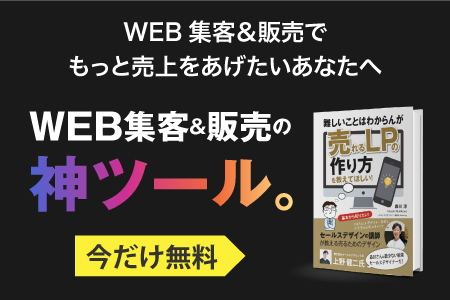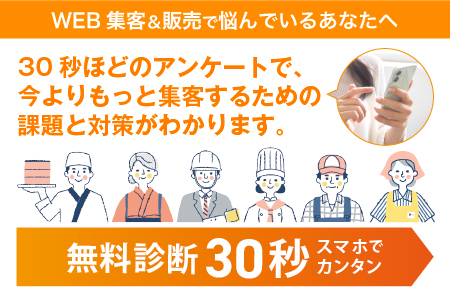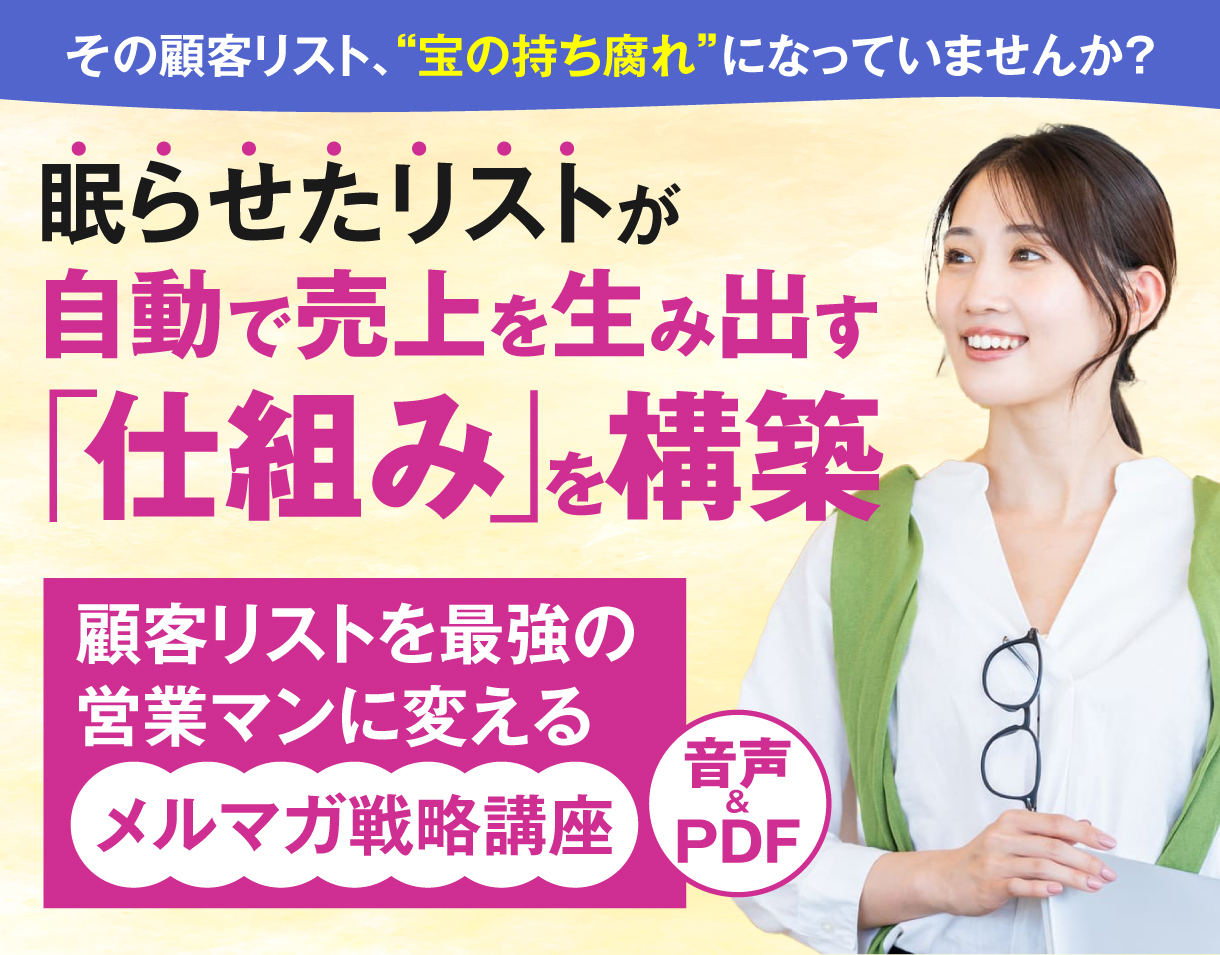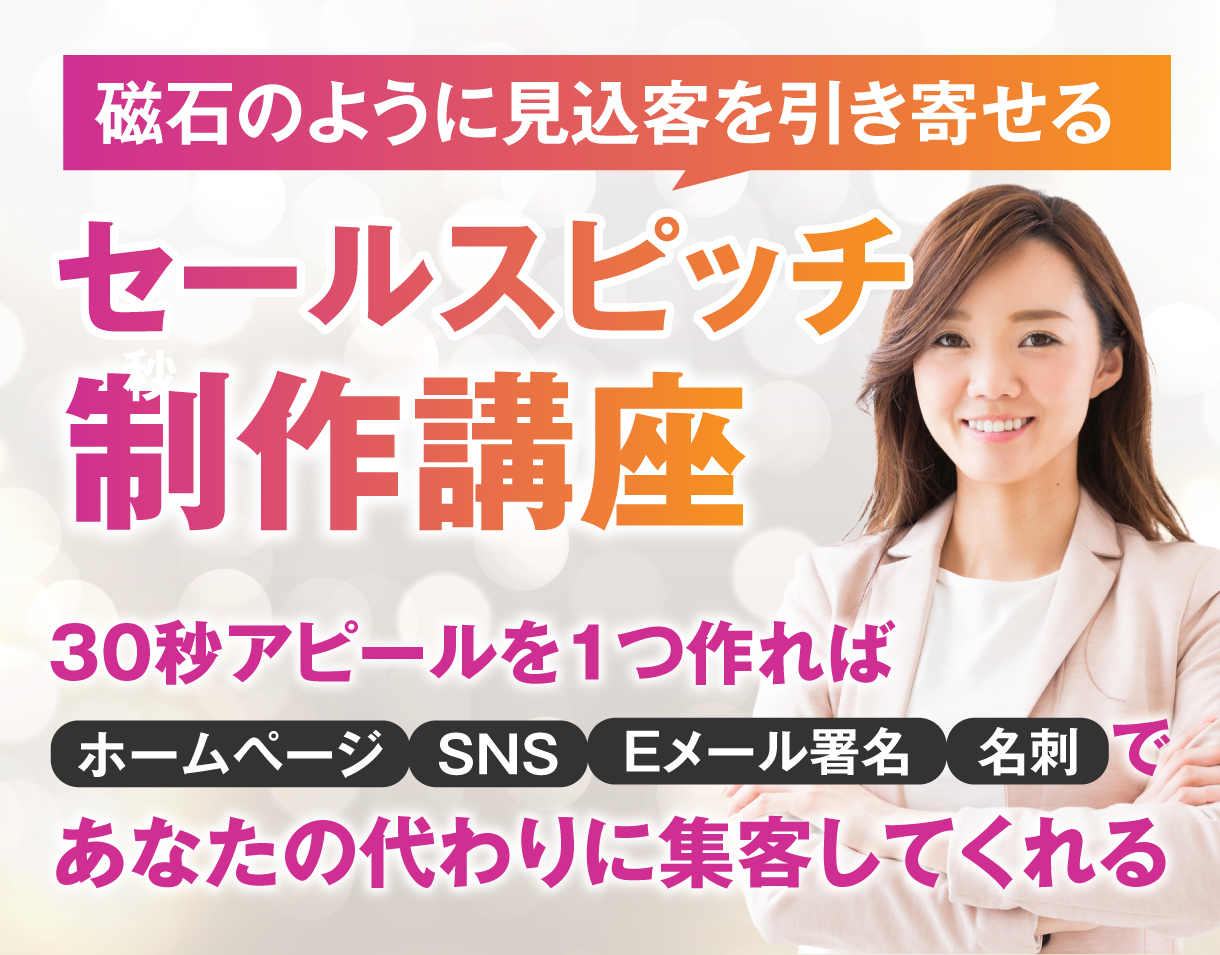「構成」と「心理」
心理トリガーという言葉、おそらくあなたも聞いたことがあると思います。
だけど、それを使えているかどうかというと、また別問題になります。
なぜかというと、ほとんどの人は、「心理」のお話よりも「構成」や「設計図」のほうが好きで、そっちばかり見てしまうからです。
広告や宣伝を組み立てるときは、媒体がどうであれ、基本的には「構成」と「心理」の2つを考える必要があります。
「構成」は、メッセージをどいう順番でどのように提示するかということです。
たとえば以前の記事でご紹介した「AIDAの法則」です。
こんな感じのお話は、だいたいみんな好きです。
いわゆる「成功のブループリント(設計図)」を手に入れたという感じになるからです。
確かに、ブループリントであることに間違いはありませんが、そこに「魂」を入れないと、いい広告宣伝になりません。
それが「心理」の部分です。
つまり「お客さんは何によって動かされるのか」「人間はどういう動機で行動するのか」というお話です。
「構成」と「心理」だと、どっちが簡単で、どっちが難しいかというと、「構成」が簡単で「心理」は難しいです。
なぜなら、「構成」はできあがっていて、誰かが開発しものを活用すればいいだけだからです。
とても簡単。
でも、「心理」は、たとえそのお話を聞いて理解したとしても、毎度毎度、お客さんの事を考えたり、リサーチする必要があります。だから難しいです。
味のない料理
でも、それがないと「魂」の抜けた作品と一緒で、似たような作りだけど、なぜか心が動かなくなります。
同じような「構成」でつくられた広告宣伝だとしても、心が動くものと、そうでないものがありますよね。
心理トリガーとは、その「心理」を刺激するものです。
あなたも聞いたことがあると思いますが、人は理屈では動きません。
感情で動くわけで、その感情、あるいは衝動とかの心理を刺激して動かすのが、心理トリガーとなります。
それがないと、メッセージは基本的に理性にアピールするわけで、頭で分かってもらっても、相手は動きません。
頭では分かるけど「欲しくない」「ワクワクしない」「テンションが上がらない」のような商品や広告宣伝ありますよね。
逆に、頭では「いらない」と分かっているけど、なぜか「欲しくなる」商品や広告宣伝もありますよね。
後者はお客さんの購買心理を刺激しているわけです。
人がどのような心理であなたの商品を買うのか。それは状況によってまったく変わります。
もちろん商品によっても変わります。
なので、絶対的な法則はありませんが、大切なことは「構成」や「設計図」のような形ばかりに捉われないことではないでしょうか?
どんな「心理」がお客さんを動かすのか。あるいは動かしているのか。徹底的に考えないといけません。
「心理」がなければ、塩や砂糖などの調味料がない料理と一緒です。
見た目は一緒なんですが味はまったく違ってきます。
あなたのお客さんは何によって動かされるのでしょうか?